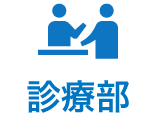循環器内科の特色
循環器内科では、虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)、心不全、心筋症、心臓弁膜症、不整脈などといった心疾患や、下肢の閉塞性動脈硬化症(末梢動脈疾患)、静脈血栓や肺血栓塞栓症、二次性高血圧の診療を主に行っています。具体的には、胸が痛い(胸痛)、息苦しい(呼吸困難)、動悸がする(心臓がドキドキする)、めまい、失神、歩くと足が痛むなどの症状がある場合は一度循環器内科を受診してください。また、急性心筋梗塞や不安定狭心症の救急患者さんには、24時間緊急での冠動脈インターベンション(PCI)を行っています。
診療内容
循環器内科では次のような方の診察をします。
循環器内科では、虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)、心不全、心筋症、心臓弁膜症、不整脈などといった心疾患や、下肢の閉塞性動脈硬化症(末梢動脈疾患)、静脈血栓や肺血栓塞栓症、高血圧(二次性高血圧を含む)等の診療を主に行っています。